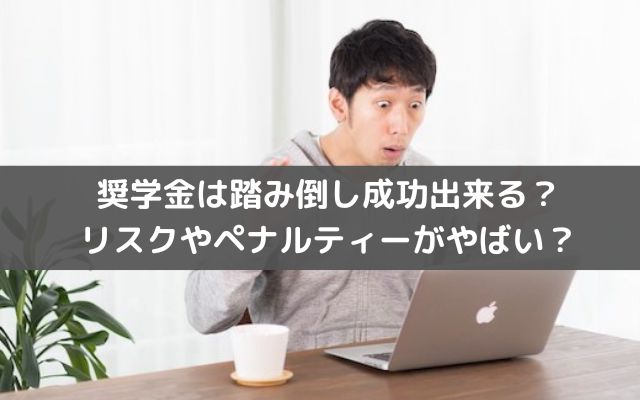大学に入学する際に奨学金を利用する方は多いのではないでしょうか。
大学卒業後には、もちろん働きながら返済しなければいけません。
月々の返済が想像以上に大変で「奨学金を踏み倒したい・・」と考えてしまう方も。
しかし、奨学金の踏み倒しには大きなリスクがあります。
ということで今回は、奨学金は踏み倒し成功出来る?リスクやペナルティーがやばいのか調査します。
成功する?リスクは?奨学金の踏み倒しについて解説します。
奨学金は踏み倒し成功できる?

奨学金を利用して大学に通ったのは良いものの、返済を負担と感じる方は多くいます。
奨学金が原因で自己破産をしてしまう人も実は多いってご存知でしょうか?
そこで奨学金を踏み倒そうと考えることもあるかもしれません。
しかし、奨学金を踏み倒すことはとても難しくほぼ不可能です。
踏み倒しに成功する割合は0に限りなく近いのではないでしょうか。
それよりも踏み倒すことによって起きるリスクの方が多くあります。
奨学金を踏み倒すリスクとは?

奨学金を踏み倒すリスクを解説します。
奨学金の踏み倒しとは?
奨学金の返済を滞納し続け時効を成立させること
返済を滞納すると次のようなことが起こります。
①延滞金がかかる
奨学金の支払いが2ヶ月遅れると、遅延損害金が発生します。
延滞金の賦課奨学金の返還を延滞すると、延滞している割賦金(利息を除く)の額に対し、年(365日あたり)3%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が賦課されます。
一般的な消費者金融の遅延損害金が年20%であることを考えると、かなり低額な利息といえます。
②催促費用がかかる
督促費用(裁判にかかる費用)を請求されることもありますので要注意。
返済したお金はこのような優先順位があり振り分けられます。
1 督促費用
2 延滞金
3 利息
4 元本
払わなければいけない費用が増えるので、返済もさらに大変になる可能性があります。
③社会的信用を失う
日本学生支援機構の奨学金制度が加入している信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センターです。
そのため奨学金を3ヶ月以上滞納すると、全国銀行個人信用情報センターに登録されます。
ブラックリストにのるので、クレジットカード作成や銀行でローンが組めなくなるので要注意です。
奨学金は踏み倒し出来ない?

日本学生支援機構などはしっかりとした機関です。
債務者に対して取り立てや裁判上の手続きをせずに放置することは考えにくいです。
保証人がいる際には、債務者本人の行方が分からないような場合でも保証人に請求が行きます。
ですので、消滅時効を待つのは非常に難しいでしょう。
社会人としてお金の管理をしっかりすることは当然ですが、学生時代に奨学金を借りる際もいくら借りるのが良いかしっかり判断する必要があります。
奨学金の踏み倒し成功は自己破産?
債務整理で自己破産すると、奨学金の返済義務を免除されたり、返済額を大幅に減額できます。
一見よさそうに思えますが、債務者が債務整理をしてしまうと、保証人に奨学金の支払い義務が生じます。
保証人は、原則として一括で支払わなければいけません。
そのため、親御さんに資金がなければ、親御さんも一緒に債務整理をしなければいけないという状況になります。
奨学金を踏み倒そうとする場合どうなる?

奨学金を踏み倒そうとすると、どのようなことが起こるのか解説します。
期間の経過と共に支払いが大変になりますので要注意。
①1~3か月支払い遅れ
滞納1ヶ月〜3ヶ月までは、日本学生支援機構から返済の督促を受けます。
延滞料が発生し、3ヶ月目にはブラックリストに登録されます。
クレジットカードが作成できないだけでなく、銀行などの金融機関のローンやカードローンも利用できないため非常に不便です。
②4~9か月支払い遅れ
3ヶ月滞納が続くと4ヶ月目から個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
それと同時に、日本学生支援機構から民間の債権回収会社に回収業務が移管され、引き続き督促を受けることになります。
③10~12か月支払い遅れ
債権回収会社からの督促を無視し続けると、日本学生支援機構から支払督促申立予告の通知が郵送で届きます。
このまま連絡がなく滞納を続けると裁判所に訴えます、という意味です。
奨学金を踏み倒す前にやることは?

奨学金を踏み倒すと考えているということは、返済が難しく悩んでいる状態ではないでしょうか。
そのような場合は以下の対処方法を考えてください。
- 日本学生支援機構に相談する
- 自治体に相談する
- 民間団体に相談する
- 家族や親族に相談する
- 債務整理を検討する
それぞれを詳しく紹介します。
日本学生支援機構に相談する
日本学生支援機構は、奨学金の貸与や返済に関する相談を受け付けています。
返済が困難な場合は、返済額の減額や返済期限の猶予などの制度を利用できる可能性があります。
自治体に相談する
自治体によっては、奨学金の返済支援制度を設けている場合があります。
詳細は、お住まいの自治体のホームページを確認するか、直接相談窓口に問い合わせてください。
民間団体に相談する
奨学金の返済問題に取り組んでいる民間団体もあります。
これらの団体は、返済に関する相談やアドバイスを提供しています。
家族や親族に相談する
奨学金の保証人には、親がなっている場合が多いです。
自分が返済出来ない場合に踏み倒してしまうと、保証人に迷惑をかけてしまいます。
社会人になって親や親族にお金を工面してもらうのは気がひけると思いますが、様々なリスクを考えると援助してもらえるなら家族や親族に相談してみるのも良いと思います。
債務整理を検討する
上記の方法で解決が難しい場合は、最終手段として債務整理を検討することもできます。
債務整理には、任意整理、特定調停、民事再生、自己破産などの方法があります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、弁護士に相談して自分に合った方法を選択する必要があります。
奨学金踏み倒しについてまとめ!
さて、今回は奨学金踏み倒しについて解説しました。
奨学金の踏み倒しはできる可能性は低く、リスクの方が高いでしょう。
督促状などを無視していると、保証人に連絡が入り一括で支払わなければいけない可能性も。
最悪の場合、財産の差し押さえもあるのでご注意ください。
奨学金を利用する際は借金ということを自覚してどれくらいで返すのかを想定して借りましょう。